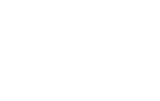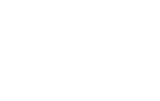|
The University of Shiga Prefecture Repository >
人間文化学部・人間文化学研究科(School of Human Cultures/Graduate School of Human Cultures) >
博士学位論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/610
|
| タイトル: | 日本中世の母性と穢れ観 |
| 著者: | 加藤, 美惠子 |
| 発行日: | 2004/03/24 |
| 抄録: | 「序論」においては、今なぜ日本における母性の歴史的研究が必要と考えるのかを、我が国の政治や社会の現状を視野に入れ論じた。
少子高齢 社会に入った日本では、少子化に対応した施策展開が急務であるにもかかわらず、国の財政状況の悪化や失業率の増加、その影響を受けた時代の右傾化のなか で、その施策展開に欠くことのできない「男女共同参画社会基本法」に基づく一連の女性政策等が、きびしいバックラッシュにあっている。結果として、子育て の社会化は停滞を強いられている。
このような社会状況にあって、元首相の「子どもを産まない女性を税金で面倒をみるのはいかがか」という発言は、この国に、女性は子どもを産むべき存在、育児 は女性生来の適正で子どもにとって母親が最善とする、女性と子どもを一体として捉え、女性の価値を「母性」のみに見ようとする傾向が、今日もなお厳然とし てあることを如実に示している。
また、子どもを持つ女性はその生き方の第一義を母性に置くべきとし、女性の価値を母性に求めようとする時代の流れを理論的に支える研究も多くある。しかし、これら の研究には、母と子の関係を近・現代のあり方のみで完結的に結論付け、歴史的視点、特に前近代の歴史に現われる母と子のあり方をその視野に入れず論じられ ているものが多い。前近代において、女性たちは全ての時代、全ての身分・階層において母性のみに生きていたのか否か。また、女性たちが母性のみにその性の アイデンティティーを求めざるをえなかったとすればそれは何時から、何故にか。各時代での検証が必要となる。
それ故に、今こそ、原始から現代までの母と子の関係を視野に入れ論じた先駆的研究である脇田晴子編『母性を問う 歴史的変遷』を踏まえ、その後の女性史研究の成 果をも視野に入れ、再度各時代の母性の本質を明らかにする必要があると考える。また、母性の本質を明らかにしようとするとき、後に述べるように女性の身体 性をもその視野に入れなければならない。女性の身体性である出産・月経がつい近年まで「穢れ」として認識されてきたことは、民俗学の報告を待つまでもなく 自明のことである。それ故に、母性の考察においては、女性と穢れ観の歴史的関係性の考察が必要と考える。
以上から、母性のみではなく、女性性にともなう穢れ観をも論じたく、論題を『日本中世の母性と穢れ観』とした。研究の対象とする時代は、社会の基礎単位たる「家」の成立期である中世とした。それは、今もなお母性のあり様が「家」と深く関わる故に、この両者の関係性の成立期での考察が母性を論じる上で不可欠と考えるからである。
まず、第1章「「女」の座から女房座へ 中世村落と母性」においては、中世村落、特に畿
内及びその周辺を中心に成立していた自治村落「惣」に焦点を当て、主に近江に残る在地文書の分析を通し、村落における母性とは何かを考察した。
本章では、まず、現在に残る村落の宮座行事、特に女性の参加はないとされる正月行事などに、女性の参加あるいは女装した男性の参加があることを確認し、本 来、正月行事などの宮座行事には女性の参加があったと指摘した。さらにこれを踏まえ、和歌山県那珂郡粉川町の王寺神社の「カクネム・シャウレム連署置文」 や滋賀県八日市市今堀町日吉神社の「結鎮ノ頭入物注文」など中世文書の分析を通し、当役としての女性の宮座への参加は、「家」の「女」(ムスメ)が本来的なものであり、それが南北朝頃から、婚姻形態の変化、婚姻圏の拡大、村落構造の変化とそれにともなう宮座の再編成などにより、家の「女」(ムスメ)から家妻に移行したことを論証した。
また当時、「惣」存立の基 盤である惣有地などの再生産手段は、村人の生活安定のために村人自身の手で維持継承されねばならず、その為には村に産まれた子どもの存在は欠くことのでき ないものであり、それ故に「惣」の継承者を産む女性が必要とされた。このような村の状況を背景に、女性(女房・嫁)の役割が次第に後継者を生む母親へと限定されていく局面をも明らかした。
さらに、在地文書の女性の寄進状などから、女性たちが生まれた村落から離れ、その祭祀からも次第に切り離されて行くなかで求めた信仰のひとつとして、如法経 信仰の存在を指摘した。彼女たちがこの信仰を受け入れたのは、子ども(男子)を産み母親になることで村落における一定の地位を確保した反面、出産とそれに 伴う月経を「穢れ」とする思想や死産は地獄に落ちる罪であり成仏できないとする思想に絡め取られていったが故だと論じた。
次ぎに、第2章「中世の女性と信仰 ―巫女・比丘尼・キリシタン―」では、第1章を踏まえ、女性たちの信仰のあり方をさらに追究しその心性にも迫りたく、考察を進めた。
まず、同じ村落に生きた男性と女性が求めた信仰を、近江に残る在地文書の寄進状の分析により比較し、両性の信仰にかける思いには極楽往生を望むことにおいては同一でも、そこに至る過程に相違があることを論じた。その相違とは、宮座の中心となる寺社や惣中に田地等を寄進し、惣村の安定した経営と村人の結束のなかに信仰をみようとする 男性と、そこから外れ個々人思い思いの寄進先の神仏と向かい合う女性のそれであった。また、女性の信仰のあり方はその背景に、婚姻形態、女性へのケガレ 観・罪業観などが大きく作用していることをも指摘した。
さらに、キリスト教の宣教師の報告書『イエズス会士 日本通信』や『フロイス 日本史』などから、当時の日本人の宗教観は現世利益を祈る「神」と極楽往生を願う「仏」に分かれてい たことを確認し、それを手がかりに、当時の女性たちの信仰に深くかかわっていた巫女や比丘尼の実態を追跡し、巫女は現世の苦悩をマジカルに解決する宗教者 であり、比丘尼は後世の救済を説く仏教者であることを明らかにした。
また、野火のようなキリスト教の広がりのなかで、特に、女性たちがキリスト教に惹かれていった契機を、宣教師の報告書を分析し、一夫一婦制の固守、堕胎間引きの禁止、女性罪業観を強めつつある仏教よりもそれに縛られないキリスト教に「希望」を見たことな
どに求め論じた。しかし多くの場合、キリスト者の信仰は日本的宗教観に沿ったものであったことをも指摘した。
さらにもう一歩踏み込み、中世の女性たちが、何故にキリスト教に惹かれていったのかを、聖母信仰に注目し、今に残る民俗、特に女座・女講などをも視野に入れ論じたのが、第2章 付論「民間信仰の脈絡からみたキリシタン像」である。ここでは、女座・女講がともに、時代が下るにつれ次第に、安産と「家」の子どもの成長を祈る女性たちの祈りの集団に変容することを指摘した。そしてそれを踏まえ、隠れキリシタンが今に伝える聖母子像の絵画史料などをも参考に、当時の女性たちがキリスト 教に求めたものは母と子が一体となって救われんがための信仰であったと論じた。
以上の各章及び付論では、文化的・社会的視点での母性を考察してきた。しかし、母性の全体像を明らかにするには、女性史の重要なテーマの一つである身体的・ 生理的な視点での考察が不可欠である。しかし、中世の女性史研究においては、なおこの視点からの考察は少なく、特に出産についてはない。第3章「中世の出産と授乳」がその視座で論じた初めての試みとなった。
ここではまず、個人的な営みと考えられがちな出産が、決して「個人」的な営みではなく、常に時代の社会・「権力」のあり方と深くかかわることを、中世のなかで明らかにしようとした。
着帯や臍の緒の取り扱いなどの出産儀礼を、平安期の『宇津保物語』などの物語や鎌倉期の『吾妻鏡』或いは中世の公家の日記などで分析し、また、摂関期の貴族 社会と中世の武家社会の出産儀礼を比較しその時代的変遷を検討するなかで、中世の支配階層においては、出産に伴う種々の慣習が主従関係の強化など政治的な 役割を果たすこと、「家」の継承の誇示など政治権力と深く結びついていることを論じた。例えば室町期、ケガレ観が拡大・浸透する時代のなかで、触穢を承知 で臍の緒の裁断が将軍により行われたのは、家父長的支配体制の堅持に欠くことのできない儀礼であったがためであると指摘した。
また、中世を通し、女性たちへの出産にともなう穢れが、拡大・強化・浸透していくこと、それとともに、「家」の構成員たる、産婦の夫、新生児にもその穢れが拡大していくこと(触穢思想の拡大)を、『拾芥抄』や『文保記』などの分析を通し指摘した。
さらに、女性性への穢れ意識は、産穢にとどまらず女性の出血全てが穢れと認識され、身分を越えた全女性への拡大・強化・浸透へと展開していったことにも言及 した。そして、その拡大・強化・浸透の背景には、「血」を忌避する伊勢神道など神道信仰の拡大の動きと、それに呼応し在地の精神的支柱である氏神の権威付けを図り、共同体の安定的経営を維持しようとする共同体成員の意思が深く関わっていたことを述べた。
また本章では、出産により母乳が出るという女性の身体的変化を視座として中世社会を見ようと試みた。古代、支配者層においては、母乳が出るという女性の生理機能が、乳母・乳父(めのと)の地位を確立させ「権力」をもたらす「道具」となったと論じた。さらに、中世は、古代・中世を通して支配者層では、産むことと、育てること(授乳・哺育)とに分断されていた女性性が、庶民の富裕層にまで拡大する歴史であったことを『日本霊異記』と『今昔物語集』の比較等を通じ指摘した。
最後に、本論では、「産まない」「産めない」こと、また、当時の堕胎・間引きに十分な言及ができなかった。中世の母性の全体像を明らかにするためには、それぞれに欠くことのできないテーマであり、今後の課題としたい。 |
| 内容記述: | 人文課第1号 |
| NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/24201k003 |
| URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/610 |
| 出現コレクション: | 博士学位論文
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|