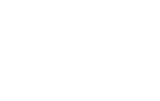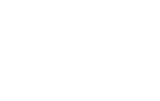|
The University of Shiga Prefecture Repository >
人間文化学部・人間文化学研究科(School of Human Cultures/Graduate School of Human Cultures) >
博士学位論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/626
|
| タイトル: | 信楽焼の考古学的研究 |
| その他のタイトル: | Archaeological study of Shigaraki Ware |
| 著者: | 畑中, 英二 |
| 発行日: | 2006/03/23 |
| 抄録: | 日本列島地域においては、生活・文化・経済的側面に陶磁器が密接に関わっており、その分野の研究が不可欠である。中でも日本列島地域における考古学的発掘調査においては、普遍的に出土するものであることから、陶磁器そのもののの生産・流通に関する研究が進められていることに加えて、年代の指標にも用いられている。
信楽は、一般に「六古窯」として知られる著名な産地の一つであり、13世紀以降今日に至るまで生産を続けている。しかし、美術品としての側面から信楽焼を研究する視点はあったものの、生産地のあり方とは切り離され、個別の作品としてとらえられるに留まっている。加えて、近年にいたるまで考古学的発掘調査も活発に行われておらず、研究そのものは停滞していた。そこで、日本列島地域における陶磁器生産のあり方を検討する上においても非常に重要な位置を占める信楽焼の通時代的な総合研究が求められていた。
本論においては、陶磁器の生産に関する文献が残されていることは稀であることから、遺構・遺物を中心に据えた考古学的な研究を進めることにより、まず、13世紀から19世紀までの生産の様相を明らかにすることを主眼とする。具体的な研究方法および成果を以下に述べる。
まず、根拠となる資料として、5世紀後半から10世紀にかけての63基の窯跡(関連資料含む)から得られた須恵器類の実測図1,512点を資料編1に掲載し、信楽焼窯跡から得られた67基の窯跡(関連資料を含む)から得られた陶器類の実測図2,039点資料および窯体構造の判明するもの16基については、遺構実測図45点を資料編2に掲載している。信楽焼については、窯跡資料と消費地資料をあわせつつ、13世紀から19世紀までを大きく5期14段階に編年した。今後の調査・研究に資することが出来ると考えている。
まず、信楽焼の開窯期の技術系統について検討するために、古墳時代以降の近江での窯業生産のあり方について検討した。その結果、古墳時代(5世紀後半)から奈良時代(8世紀)にかけては須恵器生産が盛んに行われていたが、平安時代中期(10世紀)の緑釉陶器・須恵器生産を最後に窖窯系の焼成方法をとる窯業はほぼ終息を迎えていることがわかった。
信楽焼が開窯したと考えられる13世紀代直前の近江地域においては、窖窯系の焼成方法をとる窯業はなく、黒色土器や瓦器のみの生産が行われており、その他の壺・甕・擂鉢といった貯蔵・調理形態をとるものは東播もしくは常滑から搬入されていたことが明
- 1 -
らかとなった。つまり、搬入されていたものを肩代わりするような状況で常滑窯からの技術導入によって信楽焼が成立したことが判明した。
13世紀代の開窯期においては常滑窯からの直接的な技術導入、その後独自の展開をし、15世紀後半には信楽独自の双胴式と呼ばれる窯構造をとるようになる。その後、17世紀前葉には朝鮮半島系と考えられる半地下式の登窯が導入され、18世紀後半には京都からの技術導入で連房式登窯がみられるようになる。
発掘調査を実施した窯跡および踏査を行った窯跡から出土もしくは採集した製品からは、13世紀から18世紀前半までは主として壺・甕・擂鉢といった貯蔵・調理形態の耐久財ともいうべきものを、18世紀後半以降はそれらに加えて京焼風小物施釉陶器を生産するようになったことがわかる。中でも京焼風小物施釉陶器の生産量は莫大で、発見した窯跡全体の7割弱を占めている。
流通圏については、近江一国に満たない程度の範囲を対象として壺・甕・擂鉢といった貯蔵・調理形態を生産していた。15世紀後半以降になると流通範囲を京都にまでのばし、更には量的には少ないものの茶陶の生産を行うようになり、以降侘び茶の伝統的な形式の中で生き続けるようになる。18世紀前半までは、京都を含めた地元向けの生産に終始していたが、18世紀後半には京焼の流行を受けて京焼風小物施釉陶器の生産を行うようになった。つまり、地元向けの貯蔵・調理形態の生産を基調にしつつも、茶陶の生産を行い、京焼風小物施釉陶器の生産を行うようになったことが判明した。
信楽焼は、12~13世紀に日本列島規模で数多く成立した小規模窯場の一つであった。その後、窯場の規模を拡大することなく、部分的ではあるが15世紀後半以降には京都に供給圏を広げる。ただし、瀬戸や備前などのように大規模化することなく焼物づくりの命脈を保った極めて希少な事例であったことがわかる。
17世紀以降には陶土などの次元で京焼との関わりを持ちつつ、18世紀中頃には京焼風小物施釉陶器を生産し、信楽に未だかつて無い盛期を迎えることになる。この背景には、複数の領主が錯綜し、信楽全体としての生産統制がとれていなかったことが挙げられる。ただし、この時点においても大規模化するのではなく、小規模な窯が群立するに留まっていたところに特徴がある。
以上の点から、時代を超えて共通する要素としては個々の経営規模が小さかったこと、京都と何らかの関わりがあったことが挙げられ、18世紀中頃以降については窯株が存在しなかったことが信楽固有の在り方を規定したといえるだろう。 |
| 内容記述: | 人文論第1号 |
| NII JaLC DOI: | info:doi/10.24795/24201o003 |
| URI: | http://usprepo.office.usp.ac.jp/dspace/handle/11355/626 |
| 出現コレクション: | 博士学位論文
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|